「うちの金ちゃんを返して!」
インターホンが鳴り、ドアを開けると、もの凄い剣幕の女の人が立っていた。
高校三年生のある日、僕が一人で家に居た時のことだった。
「今、誰も居ないので…」
思わず丁寧な応答をし、急いでドアを閉めた。
幸いなことに、女の人は、そのあとドアを叩くことも無く、インターホンを鳴らすことも無く、そのまま静かに帰って行った。
”金(きん)ちゃん”とは母の彼氏のことだ。
女性関係でのトラブルか?
ただごとではない状況に、当然の予想を張り巡らせた。
「今日、誰か来た?」
その夜、帰宅した母がバツが悪そうに僕に聞いてきた。
「来たよ」
僕は答えた。
「相手にしないでいいよ」
母は一言、そう言ったきり、あとは何も話さなかった。
いつもどおりの無口な態度に、安堵感があり、僕もそれ以上、何も聞き返すことはなかった・・
1989年、僕は高校に入学した。
中学とは違う、はじめての環境。新しい友人達。
少しの不安とちょうど良い期待感があった。
僕は何か打ち込めることがしたいと思い、中学から仲の良かった友人の誘いで、吹奏楽部に入部した。
顧問の先生のすすめでコントラバスを担当することになり、それからの3年間、僕は吹奏楽に真面目に打ち込んだ。
何より楽しかったのは、週末になると部活の先輩の家に遊びにいくことだった。
週末の夜になると、先輩の家に、他の先輩達も同期も4~6人ほど集まって、夜通しでトランプやかくれんぼなどの、健全?な夜遊びをしていた。
いつも時間が過ぎるのを忘れて遊び、夜明けには眠い目をこすりながら、それぞれ自転車に乗って帰っていった。
母はそんな僕には何も言わず好きに自由にさせてくれていた。
その母自身も、ある意味、自由に生活していた。
彼氏「おじさん」は、毎日、家に来て寝泊まりしていた。というより、一緒に生活していた。
僕ら子どもが居ても気にすることは無く、食事もシャワーも遠慮なく、普通に生活していた。
そんな自由を謳歌していたある週末の夜、僕はいつもの夜遊びに行く感覚で、母には何も言わずに友人と二人で港へ向かった。フェリーにて400キロ離れた本島へ小旅行することにしたのだ。
フェリーが港から離れ、夜の海を渡る。船酔いは必至だった。
あまり高い料金は払えず、低価格の大部屋に泊まることにした。大部屋にはたくさんの人が居て、みんな雑魚寝状態で一晩を過ごした。
翌朝、本島に着いた。
さすがに母には何も話していなかったので、朝になっても家に帰ってこない自分のことを心配しているだろうなと思い、僕はその足ですぐに母に電話をした。
母は状況を聞いてびっくりしていた。
いまさらだけど、申し訳なかったと思う。
しかしその小旅行では、他校の吹奏楽の見学に行ったりと、真面目に見聞を広めることに費やした。貴重な経験ができて良かったと思う。
高校生活は部活一辺倒だった。真面目に練習に明け暮れた。
なにより、吹奏楽コンクールという大きなイベントが目標だった。全国大会の予選が、毎年、本島にて行われる。
夏休み中に開催されるのだが、とにかく行くのが楽しかった。
本番ステージでの緊張感は想像以上だったが、達成感は大きな経験となった。貴重な時間だったと思う。
スコールというのか、島にはよく雨が降る。ちょうどよい雨が降り始めるのを待って、何故か僕は夜道を一人でランニングするのが好きだった。
人も車も通らない真っ直ぐなアスファルト道を、裸足でびしょ濡れになりながら駆けていた。何故かはしらないがそんな衝動が当時の僕にはあった。
誰かが見ているわけでは無いので、「かっこよさ」を求めていたのでは無いと思う。
ただ単純にスコールの中を走ることは気持ちが良かった。
高校での昼食はいつも弁当を買って食べていた。学校のすぐとなりに男子生徒に人気の飲食店があった。なんと200円でソースカツ弁当が買えたのだ。それに100円で飲み物をプラスして(当時は100円で買えた)毎日の昼食を300円ですませていた。
高校2年生頃から、授業をサボるようになった。
進学する予定も無かったので、卒業出来ればいいと、それくらいにしか考えていなかった。ただ部活だけは真面目に通っていた。
そんな僕の高校生活を知ってか知らずか、母は僕に何も言うことは無かった。
3年生になると免許を持つ友人が何人か居て、夜のドライブに出かけるのが定番になっていた。しかし、僕は早生まれで免許がとれず、友人の運転する車に同乗させてもらっていた。
当時、付き合っていた彼女が、ある日「海が見たい」と言ってきたことがあった。すぐに友人に頼んで夜の海に3人でドライブに行った。
ちょうど良い場所で車を停めてもらい、彼女は、海岸近くの低い堤防の上に座り、月に照らされた海を静かに眺めていた。
島のまわりには、魅力ある海岸がたくさんあった。
車を降りて夜の海を眺めるのは僕も好きだった。
月が出ていれば明るくて、夜でも海を見ることはできるが、曇り空だと真っ暗で波の音しか聞こえない。
たまに暗闇の中にヤシガニとかが居て、びっくりすることもある。
中学最後の遠足で行ったあの岬にも何度か寄った。夜の岬では灯台の灯りがぐるぐる忙しそうに回っているが、足下は真っ暗で転びそうになる。岬は夜よりも明るい昼のほうが僕は好きだった。
卒業が近くなってきた時期、僕は音楽関係の仕事に就きたいと思うようになった。母に進学について話しをした。もちろん学費は無かった。いろいろ考えたあげく、新聞奨学制度を利用しようと僕は決めた。母は特に反対はしなかった。
そうこうして僕は卒業を迎え、専門学校に行くことを決めた。
友人達も、それぞれの進路で島を出ることにはなっていたが、僕は受け入れ先の都合で、誰よりも早く島を出ることになった。
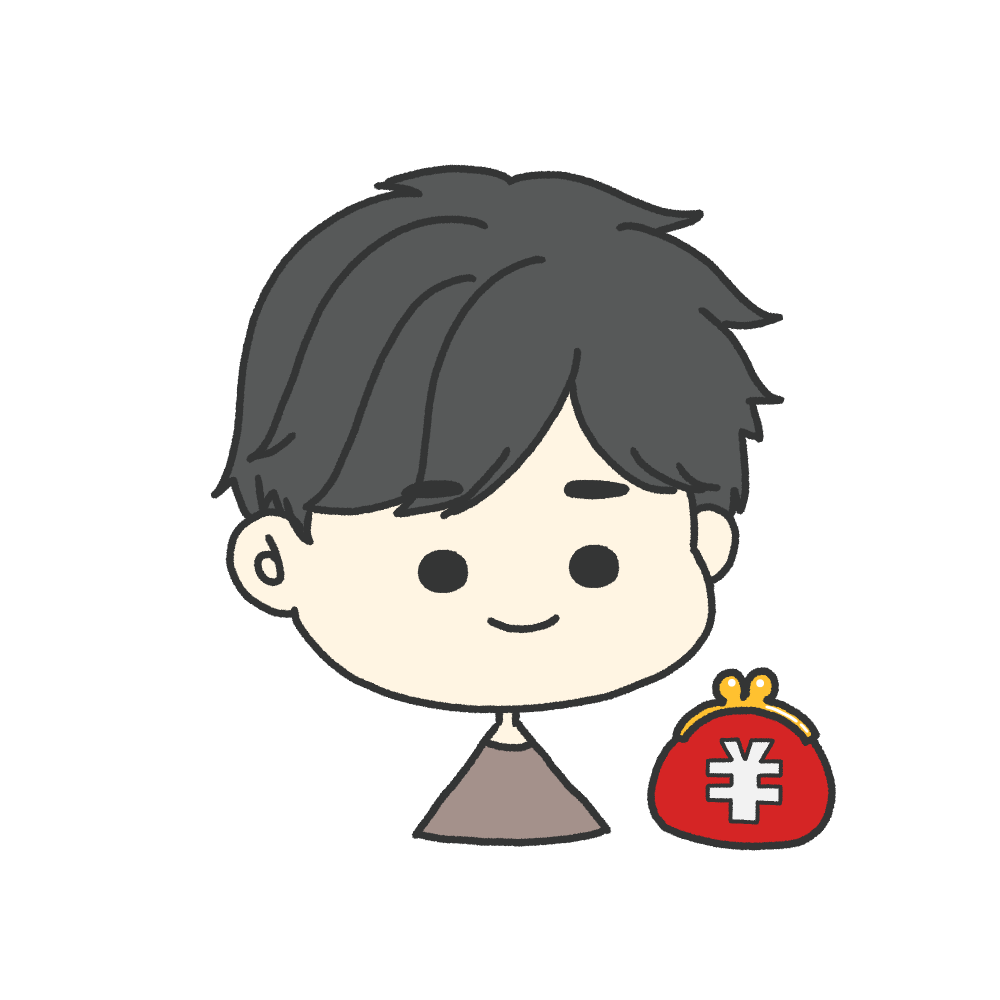 まつにい@雑記ブログ
まつにい@雑記ブログ 

